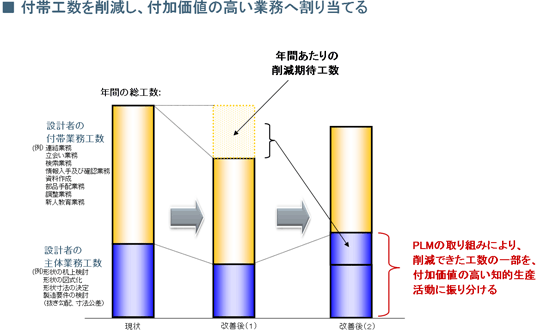機械設計者の視点からPLMのあり方を考える:メカ設計 イベントレポート(4)(2/2 ページ)
PLMは、設計者が必要だと思う範囲からでいい――ITベンダのコンサルティング現場から
「どのような基盤が、どのような要素技術が、設計・製造のデータベースとしてあったらいいのか。究極的には、大規模なBOM、構成管理を統合するシステムも必要だとは思うのですが、まずはあせらず、設計者目線で考えてやるべきでしょう」とPTCジャパン ビジネス開発推進室 ディレクターの後藤智氏は話した。
作業ごとでツールがバラバラであることに慣れている開発現場の設計者にとって、大規模な一体統合PLMとは、資金面でも、検討する時間の面でも、少々気が遠くなりそうなシステムだ。なので、これはあくまでファイナルステージだという考え方で、まずは設計者の手の届く範囲からマイペースにプロセス改善へ取り組めばいいのではないかと後藤氏はいう。
従来のコンカレントエンジニアリングでは、設計・製造力そのものを非常に重視してきた。一度確定した商品企画に基づき、具体的な設計に取り組むというやり方である。他社製と似ていてもいいから、製品を早く安く、そして高品質で作ってさえいれば市場をリードできた時代なら、この考え方でよかったのだろう。しかし、いまは設計品質だけではなく、商品企画のユニークさまでも設計段階で考慮しなければ、生き残れなくなってきている。
従来型であると、例えば企画が変更になったとき、手戻り工数は莫大となってしまう。修正をしたいのが、前の段階であればあるほど、非常に面倒な事態となる。それが企画の変更となれば、下手をすれば、一から設計のやり直し、物も作り直しとなってしまう。かといって、市場投入するタイミングを遅らせることもできない。その結果、企画の条件を完全に満たせずに中途半端なまま、要素技術も検討が十分ではないまま、製品が市場へ出てしまうことになる。
「いまの設計開発現場は、実質、設計・製造における後工程でのコンカレントエンジニアリングが大分部という状況ではないでしょうか」と後藤氏は話す。しかしこれからは、企画構想力も重視しないといけない時代だ。そうするには、企画段階でさまざまな項目に関して考え尽くされている必要がある。そうするには大規模なシステムを導入することが必要になるが、それをいきなりというのは難しい。そこで後藤氏は「車のハイブリッドエンジンと同じように、ハイブリッドな設計エンジン、つまりハイブリッドなコンカレントエンジニアリングがあってもいいのではないでしょうか」と提案する。
“ハイブリッド”とは、製品開発プロセスと設計者個人の生産性とで両輪での改善提案を行うことだという。まず設計者の業務の無駄を省いていく、つまり従来の後工程型コンカレントエンジニアリングを改善していく。そして業務がある程度うまく効率化した段階で、前工程でのコンカレントエンジニアリング導入も少しずつ検討していけばよい。
前工程でのコンカレントエンジニアリングとは、いわゆる、企画構想力の強化である。工程の早い段階で、構想モデルやレイアウト検討を迅速に3次元化しつつ、原価や規格の見積もりまでも踏まえながら、商品企画をしていくことである。ここに関わる部分を手の届く範囲からでいいから、システム統合や自動化ができないかと考えていく。
まずそれらを考えるにあたり、後藤氏は現場設計者の工数分布を提示した。
図1のグラフは、PTCのコンサルタントが同社の顧客を調査した結果であるという。
内側のグラフが実際の設計作業をするエンジニア(「設計担当者」)の作業分布、外側が彼らを取りまとめるリーダー(「設計リーダー」グループリーダー、設計課長、主任など)の作業分布である。リーダーについては、勤続10年以上の人が想定されている。
グラフから見て分かるように、担当者であれリーダーであれ、基本的に設計者の作業は、マルチプレイヤー的要素が強い。モデリングや技術検討はもちろん、外部の問い合わせ回答、情報収集、データ登録など、さまざまな作業を行わなければならない。
モデリングをしている時間そのものよりは、設計に関する情報収集をしている時間が長い。情報収集のタイミングは、モデルを起こす前だったり、モデリングの最中だったり、形状がフィックスしてしまった後だったりと、さまざまである。どちらかの作業に集中することは難しい場合が多い。
また技術検討をする際に、ミーティングは欠かせない。「ミーティングは重要な仕組みです。これをなくすことは、当然できません」と後藤氏も話す。つまり、コミュニケーションが大切となる。
リーダーは、資料作成や試験検証など雑多な作業が減る。その代わり、部下である正社員と派遣社員の管理、外注管理といった項目が加わる。先述の宮島氏の話のように、最近は派遣社員と正社員とが入り混じった設計現場が当たり前になっている。そのうえ、いまや設計拠点も日本国内どころか、海外にまで分散されている。その影響なのか、外注管理の項目は5分の1ほどを占め、その負荷が高いことが伺える。
それに、ベテランになればなるほど、それまで蓄積した経験や知識が多くなる。そして、それを頼りにする人も増える。すなわち、人から尋ねられることが多くなる。ここでもまた、コミュニケーションが大切となるということだ。
つまり設計者というのは、設計者ならではの実作業と、誰かとコミュニケーションを取りながら行う付帯業務とで2つに大別でき、それらが絡み合っているということが伺える。そして、付帯的業務は、70から80パーセント近くまでかさばっている。しかしそれは、擦り合わせを行いつつものづくりの品質を高めていくうえで大切な業務であり、なくすことはできない。
だが付帯業務の中には、例えば後追いで作る資料作成など明らかに不要な作業はないだろうか? まずはそういったことを見極める。次に、自動化したほうが何倍も仕事が早く終わる部分を見極める。このように、まず現状のプロセスの改善・改革を考えることが、PLMへ取り組むための大前提になると後藤氏は話す。そして、PLMにより削減された時間を設計検討やモデリングなどの主体業務に当てていくようにする(図2)。
また先ほどのグラフから導き出されたのは、とにかく、設計者はマルチプレイヤーだということだった。マルチプレイヤーに適したシステムとは何なのか、素直に考えてみれば、やはり「多岐にわたる作業が1個所から楽に見渡せる」「複数のツールを使わず、1つのシステムで作業ができる」「データや資料が1つのシステムで格納・管理ができる」、つまり一体統合環境が必要だということになるだろう。一体統合環境とは、実は、設計者にとってありがたい環境だといえる。
企画、プロモーション、設計、製造、出荷、その後のサービスまで一体統合管理の大規模PLMなどと、大げさに考えず、まずは設計者の身近にある業務、例えば、外注管理、設計計算、加工検討、モデリング、資料作成などの環境から一体統合することはできないかと思案し検討する。そこを基盤にし、少しずつ、統合システムを拡大して、前工程型のコンカレントエンジニアリングにシフトしていけばいいと後藤氏は考える。 そしてベンダ側もまた、そういうことに配慮した製品提供の仕方をしていけばいいのではないかという。
ITツールと設計者とのベストな関係を考える
後藤氏のいう“ユーザーのニーズに合わせて少しづつ拡大していくシステム”というのは、ユーザーと話しながら進めていく部分が大きい。設計者の現場に積極的かつ地道に歩み寄っていくことの大事さを強く認識しているのだろう。昔々からあるアナログな活動だ。
またITで自動化が進んでも、アナログな部分というのは、まったくなくならないのだろう。宮島氏は講演の中で、「ITツールに依存してはいけない部分」も挙げている。最後に紹介しておきたい。
ITツールに依存してはいけない部分
宮島氏は、ITツールでは補いきれない部分として、対人コミュニケーションを挙げた。人材不足が叫ばれる現在は、より一層、その重要性を強調するべきであると宮島氏はいう。電子メールや電子ツールの普及が、人と人との距離を遠くし、コミュニケーションが希薄になってしまっているのではないかと。それが、先述のようにコミュニケーションが重要である設計業務、そして技術伝承の妨げになっているのではないかというのだ。
例えば、電子承認ではなく、判子の承認の方がいい場合もあるかもしれない。電子メールだけではなく、直接対面して会話をしなければならない仕掛けを業務プロセスの中にわざと作る必要もあるかもしれない。ITを否定しているのではない。ITでは補えない部分をきちんと把握し、そこにあえてマニュアルの作業を加えてみるのも手だ。そう宮島氏は考えているのだ。
現場の状況を把握して整理するにしても、導入検討するにしても、稟議を通すにしても、人の心を動かさなければならない。論理的かつ正確に説得するのは必須だが、それだけではない。そしてこれもまた、ITが補えない部分である。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
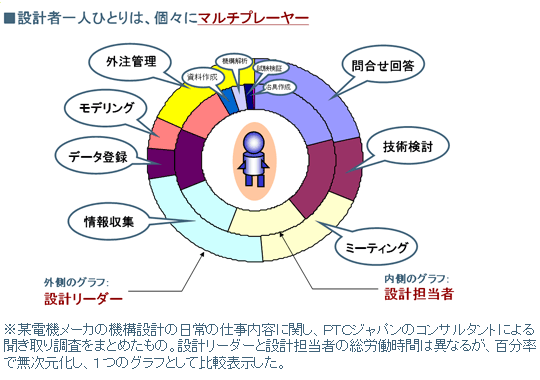 図1 設計者視点による業務分布(PTC資料)
図1 設計者視点による業務分布(PTC資料)